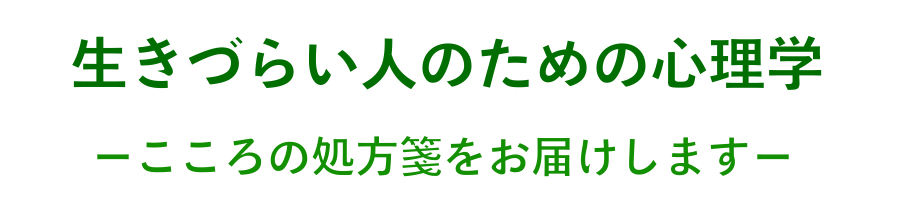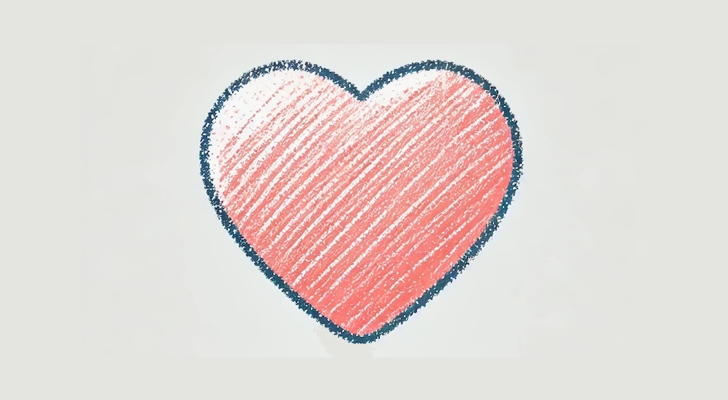【ご紹介する本】
「うつ」の効用 -生まれ直しの哲学-
(著:泉谷閑示 氏)
はじめに
突然ですが、
あなたは「生きるのがつらい」と感じたことは
ありますか?
または、
いま現在「人生がうまくいっていない」などの
悩みを抱えていませんか?
もしその原因が、
仕事のストレスや職場のプレッシャーなら……
この一冊が、少しでも人生を楽にしてくれる
かもしれません。
私自身サラリーマンですが、
仕事が辛すぎて、毎日のように辞めたいと
思っていました。
「人生このままではダメだ……」
そんな焦りから去年初夏から、
暗号資産のトレードにのめり込んで
しまいました。
その結果、
最終的には3,000万円を上回る巨額の損失。
後に残ったのは、借金だけ。
ごく普通のサラリーマンにとって、
一生かかっても取り戻せるかどうか……
そんな想像を絶する金額です。
当時の心境はまさに生き地獄でした……

人生を逆転するハズが、
自由を手にするどころか
バブル早々に呆気なくリタイア。
「生きる意味」を見失った瞬間でした。
そんなゾンビ状態のとき、
たまたま書店で見つけたのが、この一冊。
『うつの効用』という題名ですが、
うつだけに決して限らず、
「心が疲れた人」「生きづらい人」には
重要極まるヒントが詰まっていました。
この記事では、
人生のどん底を一度経験した自分が
「生き直そう」と思うきっかけになった
本書について紹介させていただきます✨
本書の要点
本書の背表紙から要約文を紹介します👇
うつは今や「誰でもなりうる病気」だ。
しかし、治療は未だ投薬などの対症療法が中心で、休職や休学を繰り返すケースも多い。
本書は、自分を再発の恐れのない治癒に導くには、「頭(理性)」よりも「心と身体」のシグナルを尊重することが大切と説く。
つまり、「すべき」ではなく「したい」を優先するということだ。
それによって、その人本来の姿を取り戻せるのだという。
うつとは闘う相手ではなく、覚醒の契機にできる友なのだ。
生きづらさを感じるすべての人へ贈る、自分らしく生き直すための教科書。
うつの根本的な回復とは──
・「治す」よりも「自分を取り戻す」
・「世間に合わせる」より「自分に正直に」
この考え方に、
私は目からウロコが落ちる思いでした。
うつに限らず、
生きづらさを解決するにはこれしかない。
そう、直感したからです。
感銘を受けたポイント
ここからは、
本書を読んで私が特に感動した、
3つのポイントを紹介します!
うつはこころのSOS。その声に耳を傾けよう。
人が「うつ」になるには、
様々な原因が絡んでいます。
しかし職場うつについては、
「頭 」と「心・体」とのズレ
この視点があると、
実にわかりやすくなります。
頭は「未来」「すべきこと」を重視。
心・体は「今」「したいこと」に素直。
この両者のニーズは、
いつも一致しているとは限りません。
・給料目当てで嫌な仕事に耐える
・周りの期待に応える
・現状維持を優先する
これらが当たり前になってくると、
本来私たちが「したいこと」が
徐々に見えなくなってしまうのです。
「心・体」がしたいと望んでいることを
「頭」で抑え続けてしまうと、
限界を知らせる”警告”が発せられます。
その一つがうつ症状ということです。
本書ではこう言われています。
「心は、頭よりもずっと重大なメッセージを送っている」
- 帰宅すると不意に涙がこぼれる
- 毎日に意味を感じられない
- 好きなことをしても心が晴れない
それらの状態が続くのは、
“こころの声”を無視してきたから。
そして”こころの声”は、
ほとんど常に正解だったりします。
だからこそ大事なのは、
生き方を見直すこと──
実際うつから全快した人の多くは、
休職中に自分と向き合った結果、
新しい生き方を選び直しています。
もちろん、
退職・転職だけが正解ではありません。
けれど、心身の不調という”ヒント”は、
新しい道への扉となるかもしれません。
組織に馴染めなくても大丈夫。
日本社会では、
「協調性」や「コミュニケーション能力」が
特に重視されますよね。
組織の中では、
「空気が読める人」「扱いやすい人材」が
高く評価されがちです。
でもそれは──
「社会に価値を与えられるか」とは
必ずしもイコールではありません。
たとえば、
アップル社のスティーブ・ジョブズに
物理学者のアインシュタイン……
彼らは組織に馴染むのではなく
その個性を存分に活かして、
大きな偉業を成し遂げています。
私自身、
組織に馴染めないことに
ずっと悩み続けてきた一人です。
コミュニケーションができない、
仕事がうまくいかない……
そんな日々が続くと、
「自分はここに居ていいのか」と
自己嫌悪してしまいますよね。
でも、
この本を読んで私は実感しました。
「そのままでいいんだよ」と。
著者はこうも述べています。
「適応とは“麻痺”の別名」
(p.127より引用)
つまり、
組織に適応できないことは
より広い視点でみた場合、
むしろ「長所」かもしれないのです。
快適な環境であれば、
そもそも「適応」の必要はありません。
「鈍感力」という言葉がありますが、
うつになるほどの「麻痺」は危険です。
また、著者はこうも述べています。
「“適応=麻痺”ができない人ほど、感性が鋭い」
「組織でうまくやれない自分」を
責める必要など全くありません。
なぜなら──
それは”弱さ”などではなく、
“繊細さ”や”豊かな感性”の証だからです。
そうした才能は、
あなたが本当に「したいこと」をするとき
必ず唯一無二の武器となることでしょう。
“死にたい” は “生きたい” の裏返し。
あまり気軽には言えませんが、
投資に失敗した私は正直なところ
“死にたい”とさえ考えてしまいました。
そんな私に──
この一節が心に突き刺さったのです。
「死にたい」と感じる人は、
実は「自分らしく生きたい」と
強く願っている。その叫びが届かないまま、
心の中で苦しみが膨らんで
いるだけなのかもしれない。持ち前の感受性や内省力が、
うまく活かされないまま
“症状”に変わっているのだ。適切なサポートがあれば、
それは“才能”として開花する
可能性がある。
(pp.94-95より引用)
思わず鳥肌が立ちました。
「死にたい」という表面の奥には、
「本当は生きたい」──
そんな感情が隠されているのです。
世の中には、
様々な困難を抱えた人たちがいます。
私の”どん底”なんて、
まだ軽い方なのかもしれません。
それでも、
私は大切な原点に戻ることができました。

「自分の人生を、自分らしく生きたい」
それが、
そもそも投資を始めたきっかけでした。
そして、
今のままの人生がつらいのなら
副業などの準備を進めればいい──
そう、前を向かせてくれたのです。
まとめ
この記事では、
私自身の自己紹介をしながら
『うつの効用 ― 生まれ直しの哲学 ―』の
感想をご紹介してきました。
本書のテーマは”うつ”と”生きづらさ”。
この記事で取り上げられたのは、
ほんの一部でしかありません。
「定年退職か、早期転職か──」
そんな悩みに答えが出るかもしれません。
“うつ”のこともよくわかります。
少しでも気になった方は、
ぜひ手に取ってみてくださいね✨
📦 本書はこんな方におすすめ
\ぜひ手に取ってみてください!/
『うつの効用』著:泉谷閑示氏
🛒 Amazonでいますぐ注文(Kindle版)
🛒 Amazonでいますぐ注文(新書)
👉 「うつ」ではないけど、毎日がつらい
👉 仕事を辞めたいと考えている
👉 周囲の人が「うつ」で接し方に悩んでいる
👉 自分に自信がなく、自己否定が激しい
👉 職場に行く意味がわからない
👉 HSP・繊細・感受性が強いとよく言われる
これらに一つでも当てはまる方には
特におすすめできる一冊だと思います。
私自身、
ボロボロの精神状態から立ち直る
きっかけを与えてもらった一冊です。
この記事の最後には、
本書の目次も収録していますので
ぜひチェックしてみてください(^^)
当ブログでは、
「生きづらさ」の解消につながるような
記事をお届けしていきたいと思っています。
ぜひ、今後ともお付き合いください。
それでは、今日はこのあたりで──
お読みくださり、ありがとうございました✨
参考資料 本書の目次
まえがき
第一章 「うつ」の常識が間違っている
1 「うつ」は心の弱い人がかかるもの?
2 「うつ」は、自覚できるとは限らない
3 「うつ」の人が遅刻や無断欠勤を繰り返すのは、責任感が足りないから?
4 遊びには行けても、会社には行けない──これは本当に「うつ」なのか?
5 「うつ」で休職中の私が、なぜ遊びに行けるのか?
6 「うつ」になりやすいタイプ──病前性格について
第二章 「うつ」を抑え込んではいけない
7 イライラは「うつ」が悪化している兆候なのか?
8 「眠れない」とはどういうことか?
9 新しい「うつ」に見られる自傷や過食の衝動
10 なぜ、「死にたい」と思うのか?──「うつ」と「自殺」の関係
11 「努力」に価値を置く危険性──「うつ」を生み出す精神的母胎
第三章 現代の「うつ」治療の落とし穴
12 「うつ」を「心の風邪」と喩えることの落とし穴
13 クスリに頼るのではなく、クスリを活用する
14 「試し出社」で会社アレルギーは消える?──段階的復帰プログラムの問題点
15 「適応」とは「麻痺」の別名──「適応障害」をめぐって
第四章 「うつ」とどう付き合うか?
16 間違っていませんか?──「うつ」への接し方
17 「うつ」の人には余計な一言?──外出や運動の勧め
18 逃げてはならない?──「うつ」の人によく向けられる精神論
19 恵まれているからこそ──世代間ディスコミュニケーションの背景にあるもの
第五章 しっかり「うつ」をやるという発想
20 「昼夜逆転」現象のナゾ──なぜ「うつ」の人は朝起きられなくなるのか?
21 何をやっても長続きしないのはなぜか?
22 「早く職場に戻りたい」──偽装された願い
23 「うつ」は“闘って”治るもの?
24 「何をやりたいのか分からない」──「うつ」の人に限らない現代人の悩み
25 夏目漱石の方法──「自分がない」空虚な状態から脱出
第六章 「うつ」が治るということ
26 現代人に蔓延する「ゾンビ化」現象
27 いまを生きよ──「パニック障害」の告げるもの
28 死んだ食事と「うつ」のメンタリティ──ガソリン補給のためだけに食べる人々
29 何もしない時間の欠乏──「有意義」という強迫観念
30 「自己コントロール」のワナ
31 「うつ」が治るとは新しく生まれ直すこと
32 「うつ」は覚醒の契機である
旧版の おわりに
新版のあとがきにかえて 「目に見えぬもの」と私たち
(本文260ページ)